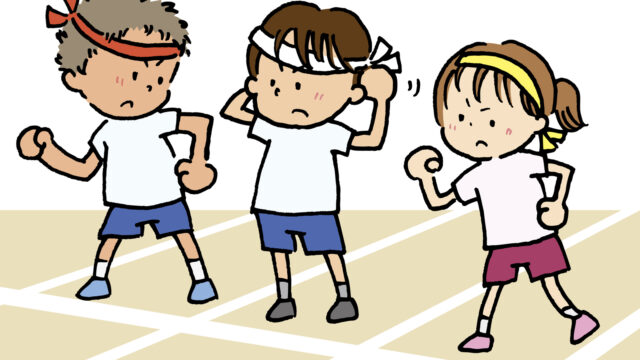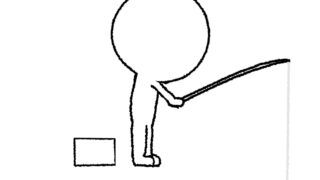介護保険負担限度額、2-3割負担、知ったうえでやっぱり働き続けていこう

記事内に商品プロモーションを含む場合があります
お金があってもなくても、医療や介護のサービスはもちろん必要です。
そのため日本では、お金が多い人は正規料金、少ない人は割引料金となっています。
そんな制度について、労働意欲、人手不足、格差問題とか正解のないことを論ずるより、とにかく自分たち家族の安心安全のために損しながらでも働き続けましょう。
介護保険制度限度額
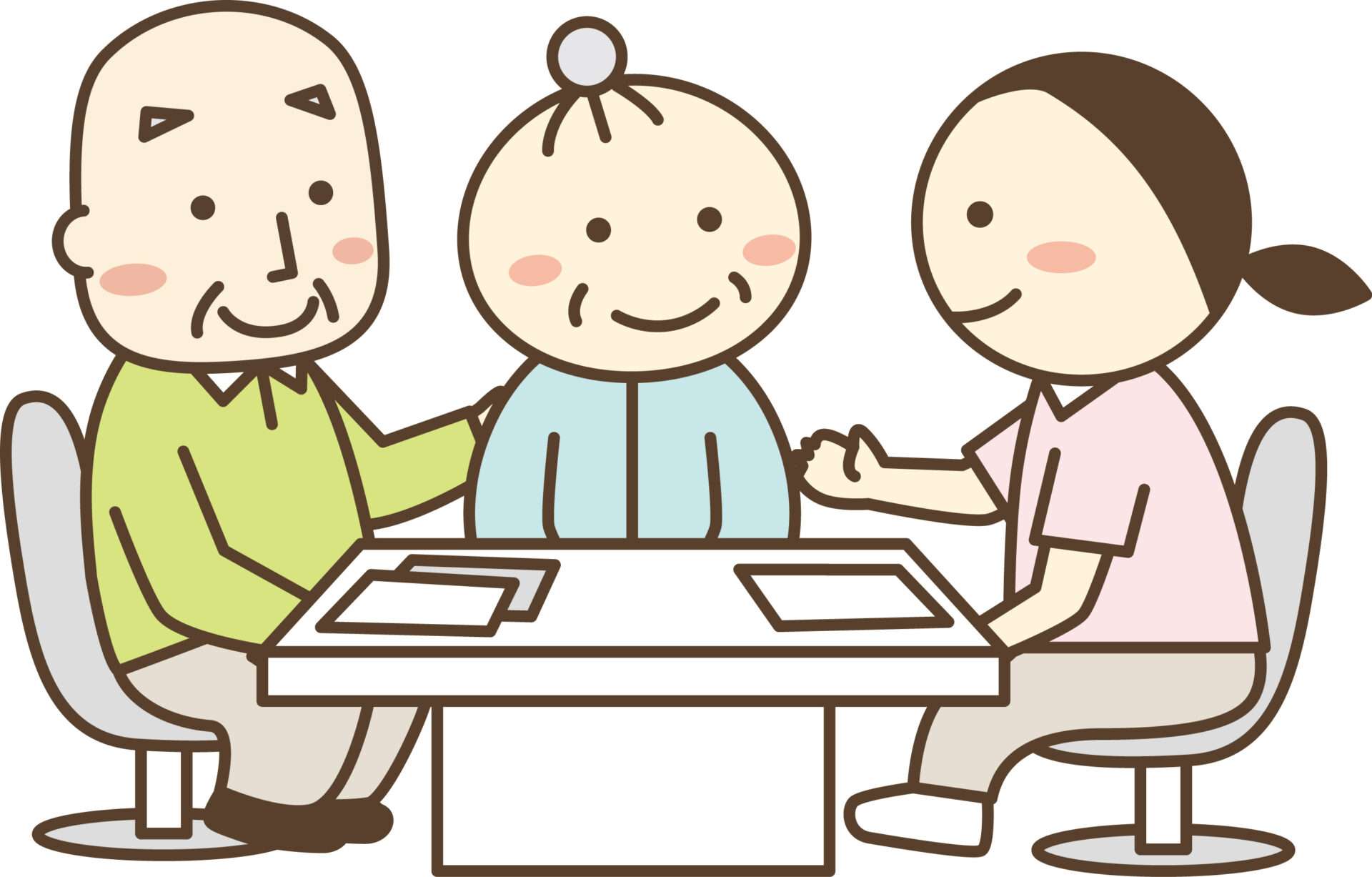
一般的に、介護保険サービスの自己負担は1割です。

そして、医療と同じように上限、負担限度額が設定されており、

その条件は 所得 と 貯蓄、
- 年間120万円以上の所得
- 夫婦1500万円以上の貯蓄

どちらかが達していれば、減額される対象からは外れます。

シンプルに、
- 厚生年金が月に10数万円
- 退職金も含めて通帳に1500万円
いわゆる老後2000万円問題への備えがあるなら、割引のない1割負担です。
2, 3割負担の人

また、医療費は現役世代が3割負担、年金生活の多くは1割負担、もちろん現役並みの収入がある高齢者なら2, 3割負担が原則です。

同様に介護保険の自己負担も、所得が現役世代並みの場合、単身で、
- 2割負担 所得280-340万円
- 3割負担 所得340万円以上
やはり支払いは多くなり、

いわゆる1割負担の人が15万円/月くらいの介護保険施設でも 、3割負担ならば20万円を超えるのです。

行政手続きの多くは前年度の所得が反映されるため、病気で動けなくなる直前まで現役だった人ほど、1年くらい高額な支払いが続きます。
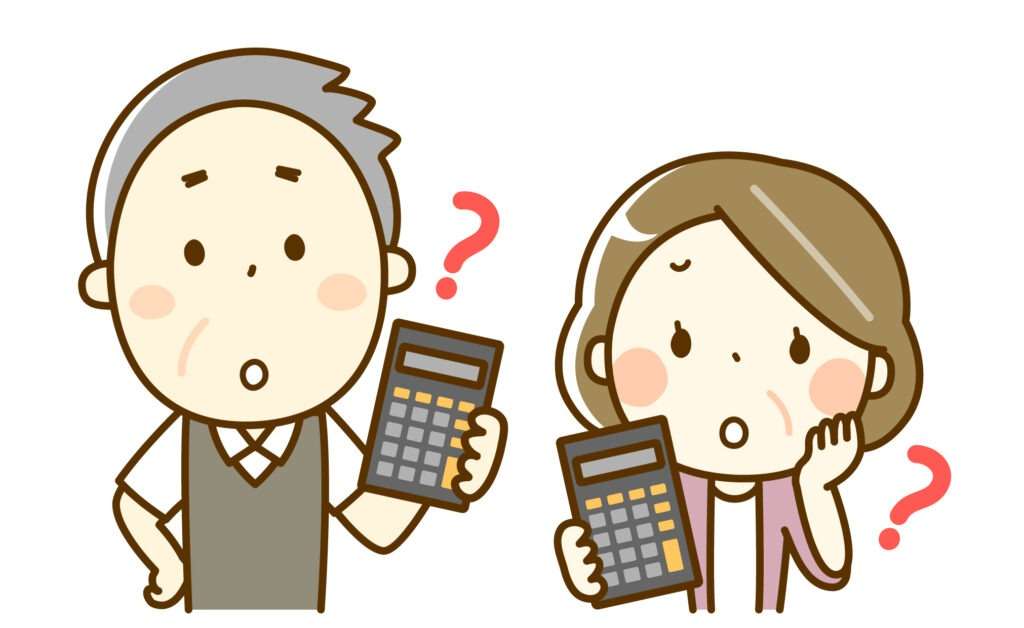
こう見ると、介護保険負担限度制度でも年金制度でも税金制度でも、払える人に払ってもらう のと 働き続ける意欲を減らさない と、両立できる仕組みはホントに難しそうですね。

まあソントクを気にするより収入のある安心を優先、ゆっくり心地よく働き続けていきましょう。
【関連記事リンク】